現代では家庭用ゲーム機に限らず、スマホ、PCのオンラインゲームと多くのゲーム媒体があります。最近の子どもにとってゲームは「当たり前にある存在」であり「友達とのコミュニケーションツールの1つ」といえます。筆者の息子も4歳から家庭用ゲーム機に触れてきました。
そのような中、多くの親御さんは「何歳からゲームをやらせてもいいのか?」「ゲーム依存にならないか心配」などとお悩みではないでしょうか。実際、息子の保育園で年長クラス懇談会の自由質問でも「就学前からゲームを与えてしまって良いか」「自身が子どものときはゲームをやらなかったので、どう関わらせていけばいいか分からない」といった悩みが挙げられました。
そこで本記事では、最近の子どものゲーム利用状況やメリット・デメリット、ゲームとの関わり方を筆者の体験談も交えて紹介いたします。
親子で話し合い、お互いが納得できる内容で、楽しくゲームと付き合っていきましょう。
子どものゲーム利用状況は?
子どものゲーム利用状況で統計結果を調べると、小学校入学時点で6~7割の子どもが家庭用ゲーム機やスマホを使用しており、その割合は学年が上がるにつれて増加しています。
この傾向は、子どもが成長するにつれて交友関係が広がり、ゲームが友人とのコミュニケーションツールとして重要になるためと考えられます。
幼少期は家庭や幼稚園・保育園が生活の中心であり、ゲームの話題も少ないですが、小学校に入ると友達との会話の中でゲームが話題に上がることが増え、オンラインでの協力プレイなどを通じて遊びの幅も広がります。
そのため、ゲームの使用については一方的に親が許可・禁止するのではなく、子どもたちの成長や目的を考慮しながら適切に向き合って決めていくことが大切です。
子どもがゲームを始めるのは何歳から?
一概に「〇歳からが良い」と言い切るのは難しいです。
なぜなら、先ほども説明しましたが、子どもたちの成長や目的を考慮してゲームに適切に向き合っていくことが大切だからです。
例えば、我が家では4歳に家庭用ゲーム機を与えたとお伝えしましたが、正直、プレイ自体は問題なく、比較的平和に遊ぶことができました。
なぜなら、ルールが単純なゲームを選んだことと、親が管理できる状況だったからです。
ソフトはマリオブラザーズ、マリオカートを選びました。一見難しそうに見えるマリオブラザーズですが、ルールは「敵はやっつける、もしくは、ぶつからない」「穴に落ちない」の2つを厳守してゴールまで行くというシンプルなものです。マリオカートも「1位を目指して車、バイクを走らせる」と単純です。
4歳では文字が読めずルールの理解が難しいと分かり切っていたため、最初は親がつきっきりで教えましたが、理解してしまえば一人で遊んでいました。また、プレイ時間の管理も「時計の大きい針が6になるまで」と指をさして伝え、キリが良いところになる度に「今大きい針はどこにあるかな?」「あと1コースだけなら遊べそうだね」と何度も声かけをすることでスムーズにやめられるようにしていました。
このように、年齢に合ったゲームを選び、適切に管理すれば、小さな子どもでも安心してゲームを楽しむことができます。しかし、いつも平和だったわけではなく、疲れていると思ったようにプレイできなかったり、時間のルールも守れなくなったりして癇癪を起こすこともありました。そういった日は、「ゲームは他の日にいっぱいやろう!」「トミカで一緒に遊びたいなぁ」などと言って一時的にゲームから離れてもらうようにしました。
低年齢のうちやゲームを始めたばかりのときは、親もつきっきりでルールやゲームとの付き合い方を教える覚悟が必要です。各ご家庭の環境もありますので、つきっきりが難しい場合は、ある程度ルールを理解、守ることができるようになった小学校就学前後に始めることが望ましいです。
ゲームの利用で起こりうるトラブル・影響は?
- 目への影響
「ゲームばかりしていると目が悪くなる」とよく言われますが、これは決して根拠のない話ではありません。
なぜなら、近距離(30センチ以内)でデジタル端末を長時間見続けることが、視力の低下や目の健康に悪影響を及ぼす可能性があるとされているからです。
公益社団法人 日本眼科医会の見解では、タブレットなどを長時間使用する子どもの視力が低下傾向にあり、注意が必要だと指摘されています。実際に筆者の息子が小学校でタブレットを受け取った際にも、使用時間を30分以内に抑え、それ以上は一旦休憩をはさむよう注意喚起のプリントが配布されました。
また、大人でも仕事でPCを長時間見ていると目がかすむことがありますが、これは画面に集中することでまばたきが減り、目が乾燥して角膜に負担がかかるためです。
このように、長時間の画面使用は目の健康を損なうリスクがあるため、適切な使用時間を意識することが大切です。
- 姿勢が悪くなりがち
ゲーム中は猫背になったり、顔を下に向けていたりなど姿勢がくずれがちです。
なぜなら、長時間姿勢を正しているのは疲れるため、リラックスすると楽な姿勢を取りがちだからです。特に、まだ筋肉が少ない子どもは、より姿勢が悪くなりやすい傾向があります。
ゲームに熱中してくると、無意識のうちに前のめりになったり、体を丸めたりしてしまいます。これは大人でも同じで、長時間デスクワークをしていると姿勢が崩れるのと同じ現象です。子どもは体幹が未発達なため、特にその影響を受けやすくなります。
そのため、ゲームのあとは、ストレッチや柔軟体操などを取り入れて身体をほぐして姿勢をリセットするようにしましょう。
- オンラインの場合は犯罪にも注意
オンラインゲームでは、犯罪に巻き込まれるリスクがあるため注意が必要です。
なぜなら、学年が上がるにつれて、友達とオンラインで協力プレイをする機会が増え、知らない人と交流する可能性も高まるからです。
親の管理下で「友達とだけ遊ぶ」と制限しているうちは比較的安全ですが、知らない人との交流が始まると危険なトラブルに発展することがあります。
例えば、「パスワードを教えてと言われ、つい教えてしまった」「裸の写真を要求された」といったケースも報告されています。
そのため、子どもが誰とゲームをしているのか、どのようなやり取りをしているのかを保護者はアンテナを張り、適度に見守ることが重要です。
- ゲーム依存への影響は?
ゲームをすることにより「ゲーム依存にならないか」といった心配の声はよく聞きますが、これは「こうすれば絶対にならない」という方法があるとは言い切れません。
なぜなら、ゲームとの付き合い方を子どもと納得する形で決めれば依存のリスクは下がりますが、最終的には子どもの性格や特性にも影響されるからです。
例えば、大人でもスマホ依存になる人とならない人がいます。趣味があったり、時間管理が得意な人は自制できますが、「即レスしないと嫌われるかも」「ゲームアプリで常に〇コイン稼いでおかないと、次の期間限定アイテムが手に入らないかも」といった不安から、ダラダラとスマホを触り続けてしまう人は依存しやすい傾向にあります。
同様に、子どもがゲームの時間管理を守れなくなった場合も、何が原因でそうなっているのかを観察し、不安を解消する方法を探すことが大切です。
お子さんが時間管理を守れなくなってきた場合、「何がそうさせているのか」をしっかり観察して不安の解消方法を探したり、ルールの再調整を考えたりしても良いでしょう。
子どものゲーム使用にメリットはある?
- 物事の目的、手段の大切さに気づく
ゲームをすることには「物事の目的を理解し、適切な手段を考える力を養う」というメリットが挙げられます。
なぜなら、ゲームには必ず「ボスを倒す」「レースで1位を取る」といった明確な目的があり、それを達成するための方法が複数用意されているからです。その中から「自分に合う方法はどれか」「必ずやらなければいけないものはどれか」を考え、試行錯誤する経験ができます。
例えば、勉強や宿題を自主的に進めるお子さんは少ないですが、それは「何のために勉強するのか」という目的が明確でないからです。算数なら「お金の計算を出来るようにする」といった目的が考えられますが、そのための学習方法は一つではありません。学校のやり方が合わなければ、別の方法を見つけないと「勉強がつまらない」となります。
筆者の息子も、繰り上がりの足し算の学校の教え方が合いませんでした。しかし、彼は「計算の答えが合うこと」を目的としていて、計算過程の記入欄でバツをつけられても気にせず、「計算の答えは合っていた」という目的の達成感から、算数嫌いにはなりませんでした。それどころか、自分なりのやり方を極め、ゲーム中でも瞬時に得点計算ができるようになり「俺、計算速いでしょ?」と自信を持つようになりました。
このように、目的と手段を意識することで、行動の方向性が明確になり、さまざまなことを続けやすくなります。ゲームを通じてこの力を鍛えることは、勉強や日常生活にも役立ちます。
- 学習体験ができる
シミュレーションゲームの場合、学習体験として良い手段となります。
なぜなら、ゲームは現実世界ではないため、失敗しても繰り返し挑戦できるからです。
例えば、車の運転といった実際に体験すると危険を伴うものでも、ゲームであれば、失敗してもケガをしません。子どもの場合「あえて失敗したらどうなるんだろう」という好奇心から選択ができ、シミュレーションゲームで結果を見ることができます。そこから「この選択をするとこうなる」という経験が蓄積されていきます。
このようにゲームの中で失敗をしておけば、現実で似たようなシチュエーションに遭遇したときに適切な判断ができるようになります。
- 興味の幅が広がる
ゲームをしていると、学校でまだ習っていないこともたくさん出てきます。そしてその中から、子どもたちは興味があることを自然と拾い出しています。
なぜなら、「ゲームが好きだからこそ、もっと内容を知りたい」という気持ちが自然に湧き上がるからです。ゲームの世界観やシステム、他プレイヤーとの交流、創作活動など新しいことに興味をもつきっかけ作りになります。
例えば、スポーツゲームであれば、ルールの詳細、有名選手の名前、出てくる国旗の名前などがあります。「ゲーム内の音楽が好き」となれば楽曲制作の職業に興味が出たり、耳コピで演奏に挑戦してみたりすることでしょう。
このように、ゲームの中にも子どもたちが知らない世界、知識がたくさん溢れています。興味を持ったものを深堀りしていけるようになれば「〇〇の知識は誰にも負けない」といった強みもでき、子どもの自信にもつながります。
ゲームとの付き合い方は親子で話し合って決めましょう
- 事前にルールを設定する
ゲームに関する各家庭のルールは必ず、ゲーム購入時に親子で話し合って決めま しょう。
なぜなら、ルールを後出ししたり、親が一方的に決めたりした場合、子どもは「なぜそのルールになっているのか」が納得できず、反発するからです。
例えば大人でも、奥さんから一方的に「子どもが産まれたんだから、飲み会は一切参加しないで」と言われたら「仕事の取引先との付き合いもあるのに」と不満が出てきます。それに反発すると奥さん側も「私だって夜の時間帯の家事と育児は大変だから飲み会くらい断ってほしいのに」とお互いに不満が出てきますよね。
それと同様で子どもも「キリの良いところまではプレイさせてほしい」「他の子は〇時間やっているのにうちは厳しい」といった言い分が出てきます。大人もルールを守らない我が子にイライラします。だからこそ、事前に親子で「なぜそのルールが必要なのか」を確認し、お互いが納得できる内容でルールを設けることが重要になります。
- 成長とともにルールを見直す
事前にルールを決めたら、ずっとそのままのルールで良いというわけではありません。
なぜなら、成長とともに子どもができるゲームの幅が広がったり、子ども自身のタスクも増えたりするからです。
例えば、最初に決めたルールが「ゲームの時間は宿題を終えた後、19:00~20:00の中で45分間まで」だったとしましょう。低学年のうちは、生活リズムもゲームの時間に合わせるなど工夫して時間の確保ができるかもしれません。しかし、学年が上がるにつれ「宿題が多くなり、ゲームの時間帯までに終わらない」「オンラインゲームを始めたいが友だちと時間が合わない」などといった困りごとが出てきます。
そういったとき「ゲームを買うときに決めたでしょ!」と最初のルールを押し付けては、子どもは反発して、隠れてゲームをやろうとしてしまいます。なので、子どもの困りごとを1つずつ具体的に聞きだし、必要に応じてルールを見直すことも考えましょう。
- ルールの具体例
具体的にどこまでルールが必要か、内容に困る親御さんもいらっしゃると思います。最後に、具体的にどのようなルールが設けられていることが多いのかを紹介します。
- ゲームのプレイ時間
・「〇分だけ」といった具体的な数字だけで考えず、「時間が来たらキリの良いところで終わる」等と柔軟に対応する。
・「夕飯後からお風呂の時間まで」といった生活リズムに取り入れる
・「30分やったら一旦休憩をはさむ」といった身体への負担を考慮する
- 優先順位をつける
・宿題や学校の準備などを優先させる
・ゲームのために宿題や片付けといった優先すべきことをいい加減にやるようであれば、罰則を作る。
- 保護者の目の届く場所で遊ぶ
・子どもがルールを守れているか、親も一緒に監督しておく
・親子で一緒にゲームをするようにして一緒にルールを守る
- 課金の制限
・子どもが小さいうちは課金機能をゲーム機の設定で制限しておく
・「課金したい」と言い出したときは、「なぜ必要なのか」を説明してもらう
まとめ
多くの事例、注意点を紹介しましたが、一番大切なことは「親子で納得した内容でゲームとの付き合い方を決める」ことになります。
何度も話しましたが、一方的に決めると必ずと言って良いほど、親子どちらも不満が出てくるからです。
せっかくみんなで楽しむために入手したゲームなのに、それが原因で不仲になってしまってはもったいないですよね。
楽しく続けていくためにも、親子で何度でも話し合い、快適にゲームと付き合っていきましょう。

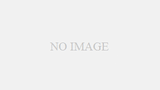
コメント